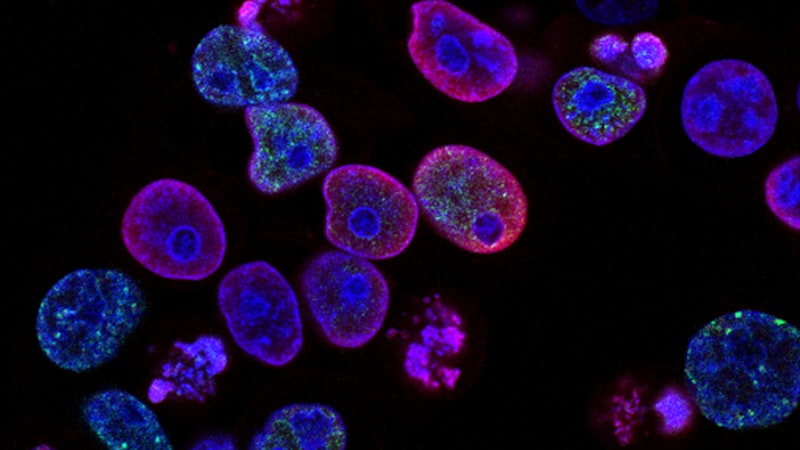免疫機能や腸内環境が気になる方に向けた、植物性乳酸菌型の免疫サポート成分です。 ラブレ菌は、京都の伝統的な漬物「すぐき漬け」から分離された植物性乳酸菌で、学名はLactobacillus brevis KB290(現在の分類ではLevilactobacillus brevis KB290)です。生きて腸まで届く胆汁酸耐性、細胞外多糖(EPS)産生による自己保護と腸内環境改善、インターフェロン-α誘導によるNK細胞活性化の3つの独自特性を持ちます。 2021年の成人試験では、熱処理ラブレ菌KB290 + β-カロテンの組み合わせにより、40歳未満のサブグループでインフルエンザ発生率が有意に低下(1.9% vs プラセボ3.9%、p < 0.05)しました。2014年の小学生試験(約3,000名)では、ラブレ菌摂取群のインフルエンザ発生率が15.7%、非摂取群が23.9%で、有意差(p < 0.001)が認められました。 ラブレ菌は、インターフェロン-α誘導によるNK細胞活性化、細胞外多糖(EPS)による腸管バリア機能強化、短鎖脂肪酸産生と腸内pH調整、訓練免疫(trained immunity)の誘導を通じて、インフルエンザ感染リスクの低減、NK細胞活性化と免疫機能の強化、腸内細菌叢の改善、過敏性腸症候群(IBS)症状の軽減に関与します。
- 主な働き:インフルエンザ予防・NK細胞活性化・腸内細菌叢改善・IBS症状軽減
- 摂るタイミング:朝食時または任意の時間、1日60億個(免疫)〜100億個(腸内環境)
- 相性:β-カロテンとの併用で相乗効果(特に40歳未満)、他プロバイオティクス併用可
- 注意:免疫抑制薬使用中、重度の免疫不全、妊娠・授乳中は医師に相談
- 食品例:すぐき漬け、ぬか漬け、キムチ(臨床用量の標準化はKB290株サプリメント推奨)
ラブレ菌とは
ラブレ菌は、京都の伝統的な漬物「すぐき漬け」から分離された植物性乳酸菌です。学名はLactobacillus brevis KB290(現在の分類ではLevilactobacillus brevis KB290)で、「ラブレ」という名称は、京都ルイ・パストゥール医学研究センターの岸田綱太郎博士によって命名されました。
ラブレ菌の独自性は、胆汁酸耐性が高く胃酸や消化酵素に強い抵抗性を持ち生きたまま腸に到達する生きて腸まで届く特性、ネバネバ成分である細胞外多糖(EPS: Exopolysaccharide)を産生して自身を保護するとともに腸内環境を改善する細胞外多糖(EPS)産生、インターフェロン-α誘導によりNK細胞(ナチュラルキラー細胞)を活性化して免疫機能を強化する免疫賦活作用の3つの特性にあります。
近年の研究では、ラブレ菌が免疫機能の活性化、インフルエンザ感染リスクの低減、腸内細菌叢の改善、過敏性腸症候群(IBS)症状の軽減に関与することが報告されています。
からだでの働きと科学的知見
ラブレ菌(Lactobacillus brevis KB290)の主な効果として、以下の4つが研究で示唆されています。
インフルエンザ感染リスクの低減を助ける(若年者):
2021年にNutrientsで発表されたランダム化二重盲検プラセボ対照試験では、20〜59歳の健康な日本人成人を対象に、熱処理ラブレ菌KB290 + β-カロテンの組み合わせのインフルエンザ予防効果を評価しました(2019年12月16日〜2020年3月8日実施)。
結果(年齢別サブグループ解析):
- 40歳未満のサブグループ: KB290+β-カロテン群のインフルエンザ発生率は1.9%、プラセボ群は3.9%で、有意差が認められました(p < 0.05)
- 40歳以上のサブグループ: 有意差なし
- 全体: 有意差なし(年齢による効果の違いが示唆)PubMed
2014年の小学生を対象とした臨床試験(栃木県那須塩原市、約3,000名)では、ラブレ菌摂取群のインフルエンザ発生率が15.7%、非摂取群が23.9%で、有意差(p < 0.001)が認められました。PubMed
NK細胞活性化と免疫機能の強化を助ける:
ラブレ菌は、腸管免疫を刺激し、インターフェロン-α(IFN-α)の産生を誘導します。IFN-αは、NK細胞(ナチュラルキラー細胞)を活性化し、ウイルス感染細胞や腫瘍細胞を排除する能力を高めます。
2013年にBritish Journal of Nutritionで発表された動物実験では、ラブレ菌KB290がマウス脾臓細胞の細胞傷害活性を増強し、NK細胞関連遺伝子、T細胞関連遺伝子、抗原提示関連遺伝子の発現を上昇させることが確認されました。PubMed
腸内細菌叢の改善を助ける:
ラブレ菌は、腸内環境を改善し、ビフィズス菌(Bifidobacterium属)やBlautia属(短鎖脂肪酸産生菌)の増加、腸内pH低下による有害菌の抑制を促進します。
過敏性腸症候群(IBS)症状の軽減を助ける:
2012年にBioPsychoSocial Medicineで発表されたランダム化二重盲検プラセボ対照クロスオーバー試験では、ラブレ菌KB290が過敏性腸症候群患者の腹部膨満感、便通異常、腹痛を有意に改善することが示されました。PubMed
作用メカニズム:
ラブレ菌が免疫機能と腸内環境をサポートするメカニズムには、以下の4つの経路が関与しています。
インターフェロン-α誘導によるNK細胞活性化:
ラブレ菌は、腸管に到達すると、腸管上皮細胞および樹状細胞を刺激し、インターフェロン-α(IFN-α)の産生を誘導します。IFN-αは、IFN-αがNK細胞表面のIFN-α受容体に結合するIFN-α受容体への結合、JAK1/TYK2がリン酸化されSTAT1/STAT2が活性化されるJAK-STAT経路の活性化、パーフォリン、グランザイムなどの細胞傷害分子の発現が増加する細胞傷害活性の増強、NK細胞がウイルス感染細胞を認識・破壊するウイルス感染細胞の排除というプロセスでNK細胞を活性化します。
細胞外多糖(EPS)による腸管バリア機能強化:
ラブレ菌が産生する細胞外多糖(EPS)は、ネバネバ成分であり、EPSが腸管粘膜層に付着して物理的バリアを形成する腸管粘膜層の強化、EPSが細菌表面を覆って胆汁酸による損傷を防ぐ胆汁酸耐性の向上、EPSが菌同士を凝集させて腸管定着を促進する菌の凝集促進という作用を発揮します。
短鎖脂肪酸産生と腸内pH調整:
ラブレ菌は、乳酸および酢酸を産生し、乳酸・酢酸により腸内pHが低下(pH 5〜6程度)する腸内pH低下、低pH環境により大腸菌、クロストリジウムなどの有害菌が抑制される有害菌の抑制、ビフィズス菌、Blautia属などの有益菌が増殖する有益菌の増殖促進を通じて腸内環境を調整します。
訓練免疫(Trained Immunity)の誘導:
ラブレ菌は、訓練免疫(trained immunity)を誘導する可能性があります。訓練免疫とは、自然免疫細胞(単球、マクロファージ)がエピジェネティック修飾により、長期的に活性化状態を維持する現象です。これにより、将来の感染に対して迅速かつ強力に応答できるようになります。
栄養素どうしの関係と注意点
ラブレ菌は、適切な用量であれば一般的に安全性が高いとされています。2009年にFood and Chemical Toxicologyで発表された安全性試験では、ラブレ菌KB290の遺伝毒性、急性毒性、亜急性毒性、亜慢性毒性が評価され、いずれも安全性が確認されました。PubMed
報告されている軽微な副作用として、軽度の腹部膨満感(稀)、ガス・鼓腸(稀)が挙げられます。
注意が必要なケースとして、免疫を活性化するため免疫抑制療法中の方は医師に相談すべき免疫抑制薬使用中、HIV/AIDS、臓器移植後などの重度免疫不全の方は医師に相談すべき重度の免疫不全、安全性データが限られているため医師に相談すべき妊娠・授乳中が挙げられます。
摂り方とタイミング
基本的な摂取量として、小学生試験での用量である1日60億個程度の免疫サポート・インフルエンザ予防目的、1日20〜100億個の腸内環境改善目的、朝食時または任意の時間(一日一回)の摂取タイミングが推奨されます。
摂取のコツとして、免疫サポート効果は4〜12週間の継続で最大化され特にインフルエンザシーズン(秋〜春)の期間中の継続摂取が推奨される継続摂取、ラブレ菌は予防的免疫サポートを目的としておりすでにインフルエンザを発症している場合の治療効果は限定的である予防的使用、ラブレ菌はワクチンの代替品ではなくインフルエンザワクチンとの併用が推奨されるワクチンとの併用、2021年の研究ではβ-カロテンとの併用で相乗効果が示唆されている(特に40歳未満)β-カロテンとの併用、腸管定着により継続的な効果を期待する生菌と保存安定性が高く免疫賦活作用は保持する熱処理菌PubMedから選択する生菌・熱処理菌の選択が挙げられます。
食品から摂るには
ラブレ菌(Lactobacillus brevis KB290)は、**京都の伝統的な漬物「すぐき漬け」**から発見された植物性乳酸菌です。
ラブレ菌を含む食品として、ラブレ菌の発祥地である京都の伝統的な漬物(赤かぶの一種「すぐき」を乳酸発酵させたもの)であるすぐき漬け、野菜をぬか床で発酵させた漬物(Lactobacillus brevis含む場合がある)であるぬか漬け、発酵過程でLactobacillus brevisが増殖する場合があるキムチ、ザワークラウト、ピクルスなどの発酵野菜(Lactobacillus brevis含む場合がある)である発酵野菜製品、標準化された菌数(20億〜100億CFU)を含む栄養補助食品であるラブレ菌サプリメントが挙げられます。
すぐき漬けとラブレ菌サプリメントの違い:
| 項目 | すぐき漬け | ラブレ菌サプリメント |
|---|---|---|
| 菌数 | 製品により大きくばらつく(10⁶〜10⁸ CFU/g程度) | 標準化された菌数(20億〜100億CFU/カプセル) |
| 菌株 | 複数のLactobacillus属菌が混在 | Lactobacillus brevis KB290(単一菌株) |
| 保存性 | 要冷蔵、賞味期限短い(数週間〜数ヶ月) | 常温保存可能、賞味期限長い(1〜2年) |
| 塩分 | 高塩分(100gあたり5〜10g程度) | 塩分なし |
| 携帯性 | 低い(冷蔵保存必要) | 高い(常温保存、携帯可能) |
| 臨床研究 | 少ない | 多数の臨床試験で効果確認済み(KB290株) |
食事からの摂取の限界:
伝統的な発酵食品(すぐき漬け等)に含まれるラブレ菌には、発酵条件により菌数が大きく変動する菌数のばらつき、すぐき漬けに含まれるLactobacillus属菌の中に臨床試験で効果が確認されたKB290株が含まれるかは不明という菌株の特定困難、すぐき漬けは塩分が高く高血圧や腎疾患の方には推奨されない高塩分、冷蔵保存が必要で持ち運びが困難という保存・携帯性、臨床試験で使用される標準化用量(20億〜100億CFU)を正確に摂取するのが難しい量の調整が困難という制約があります。
サプリメントが推奨される理由:
免疫サポート、インフルエンザ予防を目的とする場合、標準化された菌数・菌株(Lactobacillus brevis KB290)を含むラブレ菌サプリメントが推奨されます。サプリメントは、臨床試験で効果が確認された用量(60億CFU/日以上)を正確に摂取でき、塩分ゼロ、保存・携帯性にも優れています。また、生菌・熱処理菌(死菌)の選択も可能で、目的に応じて使い分けることができます。